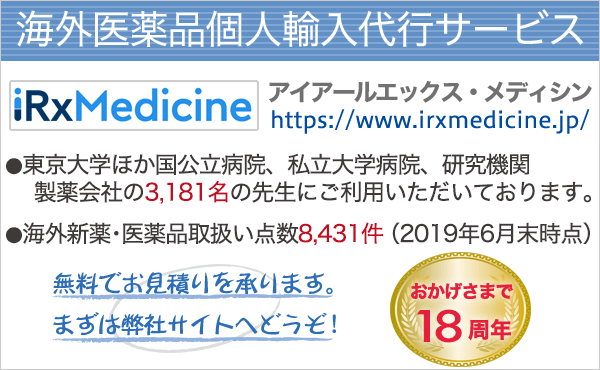更新日:2020/12/24
がんの治療方法について
がんの治療方法
がんの治療は「局所療法」と「全身療法」に大別されます。
- 局所療法:
- がんそのものに的を絞った治療。病巣が限られている場合に用いられます。
- ・病巣を切除する手術療法
- ・放射線を照射してがんを攻撃する放射線療法
- ・レーザー治療の一種である光線力学的療法
- 全身療法:
- 病巣が複数確認できたり、全身にがん細胞が侵食している場合などに用いられます。
- ・抗がん剤を使用する化学療法
- ・自己の免疫細胞を活性化し使用する免疫細胞療法
手術(外科療法)
がん病巣を手術で除去する療法で、原発巣だけでなく、他の部位に転移した転移巣も取り除きます。がんそのものを外科手術で除去する局所療法です。がんの治療法として最も基本的な治療法です。
<対象となるがん>
手術で除去しきれる場合は、ほとんどのがんが対象となります。
<副作用>
手術侵襲及び正常臓器機能の低下の可能性があります。
手術適応
手術の適応は下記ポイントについて確認を行い判断します。
- ・内科的治療の限界に達しており、外科治療がもっとも有益な治療法であるか。
- ・外科手術のもつ危険性を、その効果が上回っているか。
- ・外科手術によって、患者の生命予後が改善する可能性が高いか。
- 適応外1.がんが広がりすぎている時
- あまりにがんが広がってしまっている時、とくに、がんが原発臓器以外に転移していた場合や、播種(腹膜や胸膜に散らばった)の場合には、たとえ物理的に切除できる大きさや個数だったとしても、適応外になることがあります。
- がんが発覚された後、手術前の検査によって他の臓器への転移が見つかった場合にはその時点で手術を行わずに、抗がん剤治療や放射線治療といった別の方法を行うことがあります。
- また、完全に転移を見つけることはできません(1cm未満の微小な転移巣)し、腹膜播種や胸膜播種などは画像上では大きな変化は認められないことも多いため、検査結果では「転移巣なし」と判断して手術を行うものの、手術中に転移巣が見つかり、そのまま何もせずに手術を終了してしまう場合もあります。
- 適応外2.手術に耐えられないケース
- 手術の多くは、麻酔をかけて行います。
手術以前に、麻酔に耐えられることが確認できない場合は、手術の適応外となります。 - 適応外の症例においても、腫瘍から大量に出血をしていて、手術をしなければ生命が危ないという場合には、実施される場合もあります。
化学療法(抗がん剤)
化学物質(抗がん剤)を利用してがん細胞の増殖を抑え、がん細胞を破壊する治療法です。全身のがん細胞を攻撃・破壊し、体のどこにがん細胞があっても攻撃することができる全身療法です。
現在、抗がん剤には約100種類あり、剤型は飲み薬と注射(点滴)の2種類になります。注射には静脈注射や筋肉注射などの方法があります。他にも肝臓がんなど特定の臓器のみに抗がん剤を効かせたい場合には特定の臓器を流れる動脈にカテーテルを留置する動注という方法や、血管内ではなく腹腔内や胸腔内、脳脊髄液などの空間や体液に対して直接抗がん剤を投与するという方法もあります。
抗がん剤一覧についてもっと詳しく見る
点滴や注射による化学療法の場合は、薬を投薬する日としない日を含めた1~2週間を1コースあるいは1クールという単位でくくり、数コースあるいは数クール実施します。投与量や期間は、抗がん剤によって異なります。
がんの種類や病期次第では局所療法の場合もありますが、基本的には血液にのって全身をめぐり、がん細胞に対して作用する全身療法となります。
抗がん剤治療が治療の第一選択となることもあれば、手術や放射線治療と組み合わせることによって補助的に抗がん剤治療を行ったり、手術の前にがんの縮小を目的として抗がん剤を使用するなどさまざまな目的で抗がん剤は使用されます。
例えば
● 分子標的薬:特徴を持ったがん細胞を攻撃する
● ホルモン療法:体内のホルモンの影響を受けて増殖するがんに対して、そのホルモンを調節することによってがん細胞の増殖を抑える
なども抗がん剤治療に含まれます。
抗がん剤治療では、薬剤を単剤ではなく複数組み合わせて治療を行うことが多くなります。抗がん剤は現在でも、研究、開発が進められており、新しい抗がん剤の開発によって、延命や治療のすべがなく、治療困難であったがん患者に対する、積極的な治療が可能となりました。
<効果>
抗がん剤の効果は以下のような基準で判定されます。
1.完全寛解(CR=コンプリート・レスポンス)
腫瘍がすべて消失し、その状態が4週間以上続いている場合のことを言います。 この状態を長く続けることができれば治癒へと結びつくことができます。完全寛解が見られた場合には途中で薬の投与を中止し、再発がないかどうかをチェックしていくという段階に入ります。
2.部分寛解(PR=パーシャル・レスポンス)
腫瘍の縮小率が50%以上で、新しい病変の出現が4週間以上ない場合のことを言います。
完全に治ったというわけではありませんが、薬はよく効いており、症状のほとんどは消失しています。
3.不変(SD=ステイブル・ディジィーズ)
腫瘍の大きさがほとんど変わらない場合で、具体的には腫瘍が50%以上小さくもならず、25%以上大きくもならない場合のことを言います。がんは放置すればどんどん大きくなっていくことから、大きさが変わらないということは、少なからず薬の効果があったということを意味しています。
4.進行(PD=プログレッシブ・ディジィーズ)
腫瘍が25%以上大きくなった場合、もしくは別の場所に新たな腫瘍ができた場合のことをいいます。
<種類>
抗がん剤の薬剤の種類は、主に6種類あります。
1. 「代謝拮抗剤」といわれるもので、がん細胞の増殖を抑制する効果があります。
2. 「アルキル化剤」といい、がん細胞のDNAを破壊し、がん細胞の遺伝情報の伝達を防ぐ効果があります。
3. 「抗がん性抗生物質」といい、がんの細胞膜を破壊したり、がんのDNA合成を抑える働きがあります。
4. 「微小管作用薬」といい、細胞が分裂するのに重要な部分である微小管というものの働きを止めることによって作用を発揮します。
5. 「白金製材」といい、DNAと結合することによってがん細胞の分裂を抑える効果があります。
6. 「トポイソメラーゼ阻害剤」といい、DNAを合成するトポイソメラーゼという酵素の働きを抑える働きがあります。
単剤で抗がん剤を使用して大して効果が見られなかった場合でも、抗がん剤を複数組み合わせて使用することによって効果を発揮するという場合もあります。このことから、現在はこれらの抗がん剤の中から2~4種類の抗がん剤を併用して治療を行う多剤併用療法が一般的となっています。
<対象となるがん>
全身に転移している可能性のあるがんに対しての治療法です。白血病や悪性リンパ腫などの手術が対象とならない癌には有力な治療法となります。急性骨髄性白血病や悪性リンパ腫の抗がん剤治療における効果は高く、抗がん剤治療を行うことで、50%の確率で治癒を見込めるといわれています。
また、胃がん、大腸がん、子宮がん、前立腺がん、膀胱がんなどは、抗がん剤によりがんの縮小が期待できるがんであり、がんを小さくすることによって延命も期待することができます。逆にスキルス性胃がん、悪性黒色腫、膵臓がんにおいては、抗がん剤によるがんの縮小を望めるのは、極めてまれであるとされます。
このように、対象となるがんによって抗がん剤の効きには差が出てきます。
<副作用>
抗がん剤による治療の中でも特に化学物質を使用して行う化学療法は分子標的薬やホルモン療法に比べて、一般的に副作用が強いのが特徴です。その理由はがん細胞のみならず正常細胞も殺傷される可能性があるからです。抗がん剤の多くは、分裂・増殖を頻繁に行うがん細胞の特徴に対して、細胞の分裂を抑えこむことでがんの増殖を阻害したり、死滅させたりする作用を持ちます。しかし、分裂の頻繁な細胞であれば正常な細胞に対しても攻撃してしまうので、髪の毛の元である毛母細胞や消化管の粘膜を構成する上皮細胞、血液の元となる造血細胞や口の中の口腔粘膜などにもダメージが及んでしまいます。
抗がん剤の副作用は一度にすべての副作用が出現するというわけではなく、日がたつごとに段階を踏んで徐々に出現します。
個人差はありますが、脱毛、吐き気・嘔吐や食欲不振、白血球の減少による細菌への感染症、口内炎などの副作用が起こる可能性が高いです。また、自覚症状として症状が現れなくても、検査によって副作用症状がわかるという場合もあります。生殖機能に対しても影響を及ぼすため、抗がん剤治療の前に妊娠しているかどうかを確認したり、将来妊娠を希望している場合にはあらかじめ精子や卵子を採って保存しておいたりといったことも念頭に入れておきます。抗がん剤の治療を行うには副作用の対策を取りながら、適切な治療を進めていくことが大切です。
化学療法において生じた副作用は、つらい症状を薬で抑えたり、日常生活を工夫することによって症状を軽減することが可能であり、抗がん剤を始める際にそのリスクを考慮しながら対策をしていくことが可能となります。しかし、感染防御に働く好中球の低下及び高熱が見られた場合には抗生剤の投与や好中球を増やす薬を使用するなどの治療が必要であり、この治療をする際には入院が必要となる場合もあります。
多剤を併用して治療をする場合、副作用が重複する
薬は、副作用症状を強く出現させてしまうという観点から、使用を控えます。その代わり、他の副作用が出現する薬を使用することが多いため、さまざまな種類の副作用が見られるということもあります。
副作用と合併症の詳細についてもっと詳しく見る
がん治療と脱毛についてもっと詳しく見る
<術後補助療法>
術後補助療法とは、手術によって切除したがんの中でもわずかながら残ってしまった微小ながん細胞に対して、再発予防を目的に行われます。2006年より標準な治療法として確立された治療法です。場所を特定できないがん細胞に対して行われるので、全身療法である抗がん剤が適しているということができます。しかし、治療をしたいがんがない(見えない)ため、正確に治療の効果を測ることが難しいという現状があります。
<併用療法>
抗がん剤は新薬の開発が随時進んでいることもあり、2種類以上を組合せて行う併用療法を実施する場合もあります。最近では、免疫療法と併用する場合もあります。
他にも放射線療法と化学療法を併用して行う併用療法もあり、放射線と薬剤の相互作用による局所作用の向上や、目には見えない転移がんに対する制御ができる可能性があります。また、遠隔転移を防ぐ効果も期待できます。
肺がん、頭頚部がん、食道がん、子宮頚がんに対して特に治療効果を発揮します。
導入方法は主に3種類あり、化学療法を先行した後に縮小したがん細胞に対して放射線を当てる方法(導入化学療法)、放射線治療を先行して根治した後に再発予防で抗がん剤を使用する方法(補助化学療法)、放射線と抗がん剤を交互に行う方法(交互併用療法)があります。
併用療法の詳細についてもっと詳しく見る
<参考文献>
国立がん研究センターがん情報サービス
https://ganjoho.jp/hikkei/chapter3-1/03-01-05.html
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/attention/chemotherapy/index.html
がん研有明病院
http://www.jfcr.or.jp/hospital/cancer/treatment/medication/anticancer_drug.html
京都大学医学部付属病院参照
http://radiotherapy.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
introduction/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E7%99%82%E6%B3%95.html
日本胃がん学会ガイドライン
http://www.jgca.jp/guideline/fourth/category2-e.html
免疫療法
上記の三大治療法に加えて、免疫療法は近年「第4の治療法」として期待されています。免疫療法は研究が進められていますが、有効性が認められた免疫療法は免疫チェックポイント阻害剤などの一部に限られています。自由診療で行われている免疫療法には効果が証明されていない免疫療法もありますので、慎重に確認する必要があります。
免疫チェックポイント阻害剤(nivolmab:商品名 オプジーボ)
<オプジーボとは>従来のがん治療に新しく加わった免疫療法に用いられる新しい薬です。この登場により、切除の難しかったがんの治療、末期がん患者の延命治療なども可能になりました。
<免疫療法とは>これまでに行われてきた放射線療法や化学療法は、治療の際にがん細胞だけではなく、健康な細胞まで攻撃してしまうことが知られていました。しかし免疫療法は直接がん細胞を攻撃するのではなく、患者さんが持つ免疫機能を高めることにより治療を行います。
<オプジーボによる治療方法>オプジーボは点滴注射です。静脈から1時間以上をかけて投与します。また、1度投与して完了ではなく、数週間の間隔をあけて複数回投与します。
ただし、がんの種類により、投与量やスケジュールは異なります。
オプジーボにより、下記のような副作用が出る場合があります。
疲労、息切れ、発熱、のどの渇き、むくみ、貧血、食欲不振、筋肉痛、足や腕が上がりにくくなる、物が二重に見える、感覚麻痺、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、便秘、体重減少または体重増加、脱毛、精神状態の変化、1型糖尿病の発症
オプジーボによる治療中と治療後1年間は妊娠をしないよう注意が必要です。これは、胎児に影響が出てしまうためです。万が一妊娠した場合は医師に相談をする必要があります。また、治療中の授乳も避ける必要があります。こちらも母乳を通して乳児に影響が出る可能性があるからです。
男性の場合、オプジーボによる治療中、治療後1年間は胎児に影響が出る可能性があるため、避妊をする必要があります。
オプジーボは高額な薬ですが、年齢や収入によって負担額も変わります。そのため、金額が気になる場合は自身がどのようなケースに該当するのか調べる必要があります。
また、1か月にかかった医療費の自己負担額が一定額以上になった場合に利用できる『高額療養費制度』という制度があります。ことらも年齢や収入によって金額が変わります。事前に加入している健康保険組合から『限度額適用認定証』を入手しておくと、窓口での負担を抑えることが可能です。
制度を利用するには、人により条件なども変わるため、保険組合や病院に確認することも必要です。